2025年2月5日
外国人旅行者の消費税免税措置の廃止を
昨年12月の財務金融委員会での質疑の模様です。この問題の要点の部分を、取り出して編集しました。しっかりと取り組んでいきます。
2024年12月4日
外国人旅行者の消費税免税措置の廃止を
- 外国人旅行者向け消費税免税制度
OECD加盟国の多くでは、外国人旅行者が購入した物品に対して消費税を還付しています。国によって付加価値税、売上税などと名称は違いますが、「観光などで訪れた国で購入した物品を、そのまま自国に持ち帰った場合に免税とする」という考え方では一致しています。
これは「輸出に対しては、消費税をかけない(かけるのはおかしい)」というルールを、旅行者が買って持ち帰ったものに対しても適用している為です。「自国に持ち帰るのは輸出と同じだから」という考え方です。我が国も同様の考え方に基づいて、消費税を還付しています。
2.観光立国とは
ただ、本当に「還付」するべきなのでしょうか?
私たちは、
・「観光」に来てもらって日本と日本人の素晴らしさを知って欲しいのか?
・高級ブランド品が売れて大きな利益を得る外国の業者を喜ばせたいのか?
もう一度、よく考え直すべきかと思われます。
3.外国人旅行者の支出の7割は買い物以外
観光立国という概念が明確に位置づけられたのは2003年1月、小泉純一郎政権の「観光立国宣言」以降です。その後、なかなか進捗が見られなかったのですが、各方面の地道な努力に加えて、ビザの要件が緩和されたことなどもあり徐々に増加し、街中で外国人の姿を見ることが多くなりました。
「爆買い」という言葉が一般的になりましたから、「外国人観光客=外国人買い物客」という印象があるかもしれません。
しかし、外国人旅行者の支出に占める「買い物代」の占める割合は3割にも満たず、7割は宿泊費や飲食代です。観光先進国に比べると高いとも言われていますが、際立って高い訳ではありません。ほとんどの外国人旅行者が、必ずしも「買い物目当て」で来ているのではないことが分かります。
この7割にかかった消費税は、もちろん還付などしていません。また「5000円以上」という基準がありますから、この買い物代のすべてが免税という訳でもありません。しかも、観光客が「モノ消費」から「コト消費」へ移ってきていることから、買い物代の割合は減少傾向にあります。
- 免税制度の悪用
一方、この「外国人旅行者向け消費税免税制度」を悪用した事例が多発しています。たとえば、昨年の調査では「免税店で1億円以上の買い物をした外国人観光客」の数が680人にものぼっていました。とても実需とは考えられません。
しかも、「免税店で買い物をして日本国内で転売して利益を上げた」として摘発しても、「単なる『買い子』という手先でしかないために支払い能力がなく、徴求出来ていない」と担当者が非常に悔しがっていました。
その防止策として、来年度からは制度そのものを変えて、「買い物時点で消費税を徴求し、後で払い戻す」ことになりました。これにはシステム対応が欠かせませんから、大規模な投資が必要となっています。
日本に観光に来てもらって日本と日本人の素晴らしさを知って欲しいので、そのために大規模な投資をするのは大歓迎です。しかし、税金を返すために、さらに投資をするというのは如何なものでしょうか?
したがって、私は一貫して「免税措置の廃止」を訴えており、先日の自民党の税制調査会でも提言しました。
ちなみに、OECD加盟国すべてが、免税措置を講じている訳ではありません。アメリカで買い物をして、店頭で払った売上税は戻って来ません。制度の悪用に手を焼いたイギリスは、2021年に「旅行者向け付加価値税還付制度」を廃止しました。イギリスの付加価値税の標準税率は20%ですから、免税目当ての買い物旅行者にとっては大変な事態です。
- 観光立国推進基本計画
2023年3月に閣議決定した「観光立国推進基本計画」では、冒頭で「旅のもたらす感動と満足感」「観光により地域の魅力を発見」「観光を通じて異文化を尊重し、世界の人々と絆を深めることは、草の根から外交や安全保障を支え、国際社会の自由、平和、繁栄の基盤を築く国際相互理解を増進する」とうたっています。
「免税店での買い物を促進し、国内消費の底上げを図る」などという言葉は、どこにもありません。
一方、インバウンドには光と影があります。消費が増えることは経済にとってプラスですが、オーバーツーリズムや治安の問題などを避けては通れません。きちんと消費税を徴求し、増えた税収を影の部分の対策に投じていくべきです。
財務省によれば、2023年の訪日外国人観光客の「免税購入額」は約1兆5855億円でした。大半は10%の消費税率が適用されていますので、約1600億円が還付されたと推計されています。今年の訪日客は昨年より3割以上増加して約3300万人、年間消費額は約8兆円となると予想されています。その30%が買い物代だとして、2兆4000億円の10%は2400億円です。
7月の観光立国推進閣僚会議では「2030年に6000万人」という数字も出ました。一刻も早くこの措置を取りやめるべきだと思われます。
6.外国人の本音
外国人の知人と話すと「日本は本当に安いね」と言います。聞いていて気持ちのよいものではありません。「だったら、免税でなくても買い物するか?」と尋ねると「する、する。それでも安い」と言われました。
これは、為替の影響だけでなく、長い間のデフレで「値付けそのものが低く設定されている」からではないかと思います。それならば、消費税を払ってもらおうではないですか。
2024年10月13日
新聞折込:鶴見区、神奈川区


スライドショーはこちらから
本日、神奈川3区内の主要な新聞に折り込みました。「強い経済で、優しい社会を。」そして何と言っても、皆さんの生命と財産を守るのが政治家の使命です。
2024年10月10日
タウンニュース:強い経済で、優しい社会を。
「足腰の強い経済」という土台があってこそ、皆さんの生命を守り、生活を支え、子どもにもご高齢の方にも優しい社会を作ることが出来ます。引き続き、しっかりとした政策の実現に取り組んでいきます。
-1-500x354.png)
-2-500x354.png)
今朝の駅頭から、新しいチラシになりました。テーマは「憲法改正」です。空理空論ではなく、我々が置かれている現状をしっかりと認識した上で、憲法審査会の委員として冷静な議論を進めていきます。
#中西けんじを応援 #鶴見区 #神奈川区
+++++++++++++++++++++
冷静な議論を ―憲法改正―
厳しい現実
ロシアは、国際法と国連憲章を無視して、今日この時間もウクライナに攻め込んでいます。台湾有事に関して「日本の民衆が火の中に」と、中国大使が我々の目の前で発言したことはご存知の通りです。その中国は、この10年で軍事力を何倍にも強化しました。長距離ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮が核武装を進めていることは間違いありません。日本は不穏な軍事大国に囲まれています。
大切なのは外交努力と抑止力
こうした中、まず優先されるべきなのが、外交努力であることは言うまでもありません。わが国は戦後一貫して平和国家として歩んできました。法の支配を尊重し、いかなる紛争も力の行使ではなく平和的・外交的に解決すべきであるとの方針を変えるべきではありません。
しかし、今の日本が置かれている状況を冷静に考えると、皆さんの命や暮らしを守り抜くために「自分の国を自分で守る」ための抑止力を高めていく、つまり相手に対して「日本を攻めても目標を達成できない」「三倍返しにあってしまう」と思わせることが必要です。
ところが、私たちが大切に護ってきた憲法が、その努力の妨げとなってしまっています。
「戦争放棄規定」は当たり前
第一次世界大戦の悲惨な体験を経て、世界各国は国際連盟を作った上で、「紛争解決の手段として戦争を放棄する」とした「パリ不戦条約」を結びました。したがって現在でも150近い国の憲法に、「平和条項」が盛り込まれています。
しかし、当時63か国がこの「不戦条約」を結んでいたにも拘らず、さらに大規模な第二次世界大戦が起きてしまいました。
「平和を愛する諸国民を信頼」したいのですが
それでも、戦勝国も敗戦国も「もう二度と戦争はしたくない」という気持ちが、強まることはあっても弱くなることはありませんでした。
そこで、新たに定められた日本国憲法では、「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼」するので、戦力は持たず戦わないという形で「パリ不戦条約」の理想を改めて掲げた訳です。これには、「新たに出来た国際連合の集団安全保障によって、世界の平和が守られる」ことが大前提となっていました。
ところが、その国連安全保障理事会の常任理事国ロシアが、ウクライナに武力で攻め込んでいる訳ですから、現実はまだまだ不戦条約の理想とはほど遠いところにあります。
したがって「第9条があるから平和が保たれる」という考え方は、空想的平和主義と言わざるを得ません。哲学者の田中美知太郎京都大学名誉教授は、皮肉を込めてこう言いました。
「平和憲法で平和が保てるのなら、台風の日本上陸禁止も憲法に書いてもらえば安心して寝られる」
解釈改憲では無理があります
憲法を改正するには、非常に高いハードルがあります。そこで、苦肉の策として考え出されたのが「自衛のための必要最小限度の武力を持つことは、憲法上許されると解釈している」という解釈改憲です。
しかし、憲法学者の7割が憲法違反だと言い、どの教科書にも「政府は違憲ではないと言っているが、憲法上の問題があるという意見がある」と書かれています。
この状態のままで「非常時には命をかけて国民を守ってください」というのは、あまりに理不尽です。その場しのぎの解釈ではなく、自衛隊を憲法の中できちんと位置付けるべきです。
占領下の基本法(憲法)を廃止したドイツ
ドイツは占領が終わると、占領国が決めた基本法(憲法)を廃止して新憲法を作りました。というのも、国際法(ハーグ陸戦協定)では、占領が終わった後にまで有効な憲法を定めることが許されていないからです。そして基本法(憲法)の第11条に「侵略戦争の遂行を準備する行為は違憲である」と明記した上で、1955年から正式に再軍備を開始しました。
一方、今の日本国憲法は「新憲法」を定めたのではなく、「明治憲法の改正版」という体裁がとられました。しかし、完全に違う内容になっていますから、これは「国際法違反」という批判を避けるための目くらましです。
憲法を「護る」ということ
憲法を護るということは、条文に指一本触れさせないということではなく、最高法規としての役割を果たすことを護るということだと思います。
「現実と合っていないよ」「憲法にはそう書いてあるんだけどね」などとなると、国民の皆さんにとっての憲法は「護るべき最高法規」ではなくなってしまいます。
現実と乖離している点をきちんと改めていくことこそが、本当の意味で「憲法を護る」ということではないでしょうか。
今朝の投稿でお知らせした通り、今日から新しいチラシになりました。「強い経済で、優しい社会を」
政治は民間企業や個人が活動しやすくするために規制改革や環境整備をします。経済活動が活発になり税収が増えることで、医療や介護、子育てをはじめとした皆さんの暮らしをより良いものにするための政策を推し進めることができます。
++++++++++++++++++++
強い経済で、優しい社会を。
「タフでなければ生きていけない。優しくなければ生きている資格がない」という有名なセリフがありますが、私は「経済が強くなければ生きていけない。皆さんの暮らしに優しくなければ生きている資格がない」と思っています。だから、「強い経済で、優しい社会を」です。
シン・NISAスタート
日経平均が34年ぶりに最高値を更新した要因のひとつとして、「NISAの大幅な拡充」を専門家がこぞって挙げています。
「中途半端な改正ではなくインパクトのある大改革を行なわなければ、いつまで経っても『NISAって何?』のままだ」
「巨大な個人資産の山が眠り続けていては、誰も幸せにならない」
と、自民党の財務金融部会長として制度の抜本的な見直しと大幅な拡充を実現しただけに、相場の大きな節目に何とか間に合ったと少しほっとしています。
海の色が変わった
ただ、国際金融市場で20年以上も「市場」と格闘した経験があるので、「上がった。上がった」と能天気に喜ぶつもりはありません。相場には、上げもあれば下げもあります。
とはいうものの、株式の専門家の間で「株価には『名目の経済活動』に連動する性質がある」という見方が有力であることも確かです。これは「デフレ脱却」という変化が本物であれば、長期的には株価にとってプラスであるということです。私が「恒久化」を強く主張したのは、堅実な長期投資をしっかりと支え続ける制度にしたかったからです。
日経平均の最高値更新は、「相場の潮目が変わった」といった流れの変化の話には留まりません。長年のデフレ脱却に向けた努力によって、株式市場という「海の色が変わった」ということだと思います。
皆さんのためのNISA
NISAに対して「国民の資産を海外に流出させているだけだ」という批判があることは承知しています。「オルカン」と呼ばれる「日本を含む世界中の株式に投資する商品」の売れ行きが好調ですから、「流出」していることは間違いありません。私自身は「日本の企業に投資をして欲しい」と思っているので、とても残念です。
しかし、「資産運用立国」は日本の企業や政府、ましてや金融業者のためではなく、国民の皆さんのための政策です。「日本だけではなく世界に投資したい」と考えた皆さんが「オルカン」などを選べない制度にするのは間違っていると思い、「投資先は日本株のみ」などという制限は設けませんでした。
「日本」の商品の充実を
むしろ、私自身は「日本株関連の商品の品ぞろえが足りていない」と感じています。また、オルカンのような「インデックス・ファンド」に、プロが積極的に運用する「アクティブ・ファンド」が勝てないという考え方にも、必ずしも賛成していません。
投資にあたって取れるリスクは、ひとりひとり違っています。皆さんが投資先や投資手法を自由に選ぶことが出来るのが本当の「資産運用立国」であり、その手助けのためにNISAという制度があると考えていただきたいと思います。
「賃上げ」を訴え続けて八年
日本の家計の金融資産のうち、株式と投資信託の割合は合わせて約15%です。証券口座の開設が急増しているので、これからは増えると思いますが時間がかかります。したがって、経済の好循環には「賃上げ」が絶対に必要です。
国会で「過去最高益を叩きだした企業の労働組合が、ベアの要求を見送るとは何事か」と、経営者も組合もデフレマインドに憑りつかれていること指摘したのは2016年でした。ただ、わが国は自由主義国家ですので、私企業の賃金に政府が直接口を挟むことは出来ません。その後も再三再四取り上げて税制面から後押しをしてきましたが、結果は芳しくありませんでした。
「空気」を変えよう
しかし、あきらめてはいません。山本七平氏の「空気の研究」にある通り、わが国では「空気」が大きな役割を果たしてきています。そこで、「コーポレートガバナンス・コードの中に、『従業員との対話だけを担当する取締役を置く』と定めて、ステークホルダーとしての従業員の権利を明示すべきである」という突っ込んだ提案を改めて国会で行ないました。「賃上げが必要」という空気を、さらに大きくしていきたいと思います。
「経済の中西」として、これまでも、そしてこれからも、経済に関する正しい理解をもとに、皆さんの暮らしを豊かにするための政策を推し進めていきます。
++++++++++++++++++++++++++
<<自信を持って前へ>>
皆さんの「生産性」が低いってホント?
「日本の生産性は低い」「もっと効率よく仕事をするべきだ」という意見を耳にすることがよくあります。きちんとした計算式を使って出した「数値」が並んだ「OECD38カ国中27位」というランキングを見ると、「そうか。もっと頑張らないと!」と思いますよね。
ただ、人種や国籍、生い立ちなどが異なる人たちと一緒に働き、観光ではなく実際に仕事をするために世界の色々な国を訪れた経験からすると違和感があります。いくらバブルの崩壊を経験したとは言っても、かつてジャパン・アズ・ナンバーワンと評価された日本の生産性がこんな位置にまで落ちているとは思えません。
どこかおかしいですね
外国人が首都圏の路線図を見ると、その規模の大きさと複雑さに驚きます。さらに電車に乗ると、たった1分遅れただけなのに「申し訳ございません」というアナウンスがあるのでもっと驚きます。
そんな日本に10年以上滞在し、先日帰国した外国人の友人からこんなメールが来ました。
「私が生まれ育った無礼者と怠け者の国に戻りました」
あれ?そうなんですか??
海外でこんな経験をしたこともあります。87ドルの物を買って100ドルを出したら、「88、89、90」と1ドル札を1枚ずつ置いていき、最後に10ドル札を置いて「はい、これで100ドルね。サンキュー」。
そんな国で「1ドル札はかさばるから、おつりで10ドル札を2枚もらおう」と107ドルを出したりしたら、「多すぎる(ナニコレ?)」と間違いなく7ドルを先に突っ返されます。海外の店員さんは、暗算どころか引き算が出来ないと思った方が間違いありません。
これが世界標準なのですが、日本の生産性はその国々に大きく劣っているとされています。
本当の生産性は測れません
実は「OECDが計算した生産性」というものは確かにあるのですが、経済学者などが「真の生産性」と呼べるような数値の計算には、まだ誰も成功していません。しかも、その「OECDの生産性」には重大な欠陥があります。
たとえば、あるタクシーが8時間走って売り上げが1万円の時に、OECDの計算式によると1時間当たりの生産性は1250円です。このタクシーの売り上げが10万円になると、生産性は10倍の1万2500円に跳ね上がったと計算されます。
これが運転手さんの努力の結果であればうれしいのですが、「景気が良くなってお客さんが増えた」と考える方が自然でしょう。OECDはGDPという国全体の売り上げ(正しくは付加価値)を使って、これと同じ計算方法で出した「生産性」を発表しています。
つまり、OECDの生産性とは、「景気が良ければ上がる」「儲かれば上がる」というだけのものなのです。
犯人はデフレ
日本は長い間デフレに苦しみました。デフレとは需要が足りないことです。お客さんが乗ってくれなければ、どんなに走っても稼げませんからタクシーの生産性は下がります。状況が悪い中で、よい成果を上げるのは簡単ではありません。
雨が降っている時に氷点下の球場で試合をさせられたら、佐々木朗希投手でも160キロ台の速球を投げ続けることは出来ないでしょう。大谷翔平選手は、豪快なホームランを飛ばすほどのフルスイングが出来ないと思います。日本の置かれた状況も同じでした。決して「生産性」が低かった訳ではありません。
自信を持って前へ
しかし、2013年の政府と日銀の共同声明以来、日本経済を取り巻く環境は非常に良くなりました。長く続いたデフレから抜け出し、秘めていた力を発揮し始めた日本に世界中が注目しています。高い教育水準と技術力を誇り、1億2千万人を超える人口を擁する巨大な経済が、ようやく普通の状態になりました。「OECDの生産性」も当然上がり始めます。
もちろん「仕事が終わっても、上司が帰るまで帰りづらい」「ファイルを添付してメールで送れば済む資料を、わざわざプリントアウトして持参する」など、個別には改善をしていくべき点があると思います。しかし、トヨタ式カイゼンに象徴されるように、我々はひとつひとつ丁寧により良いものに変えてきました。むしろ、日本の組織が得意としてきたことです。
これまでも、そしてこれからも、経済に関する正しい理解をもとに、皆さんの暮らしを豊かにするための政策を推し進めていきます。
1年半前に「税収は上振れているが、これまでと違い景気回復が極端に二極化している。Kの字の下の部分を念頭においた経済政策を行なうべき」と「上振れ論」の先鞭をつけました。税収が70兆円に乗るということで注目が集まっていますが、地に足のついた議論を続けていきます。
私が国会で税収の予想外の上ブレと「K字回復」を挙げ、「二極分化」をしっかりと認識した上で「K字形の下の線で苦しんでいる方々に支援の手を差し伸べるのが政治の役割である」と指摘したのは1年半前です。
引き続き「成長と分配」の問題に取り組んでいきます。
「TEAM鶴見」と「TEAM神奈川」のチラシが新しくなりました。皆さんの生活をより良いものとするために、市・県・国が一体となって頑張ります。

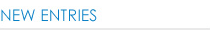




-1-500x354.png)
-2-500x354.png)


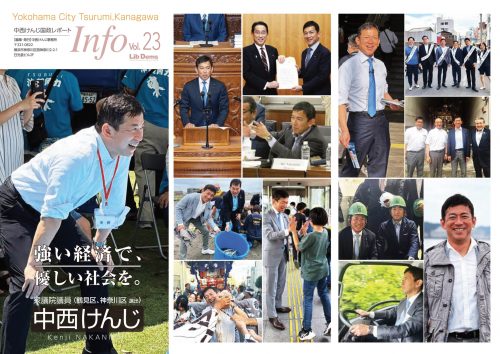

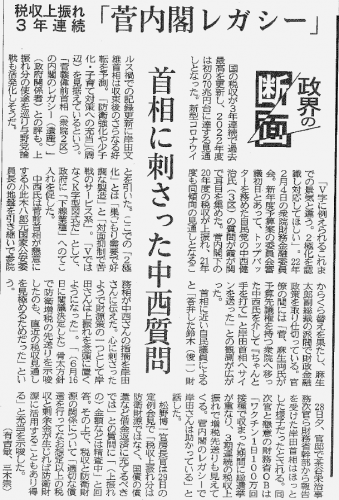
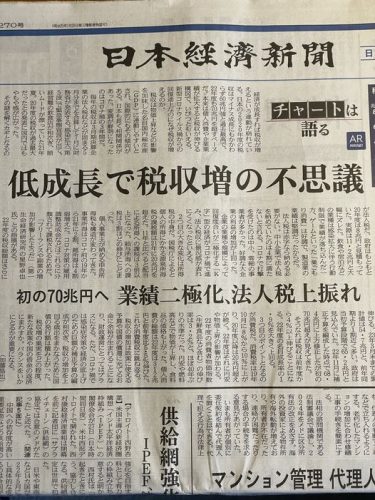


v.1-2-354x500.png)
